固定資産の取得と減価償却
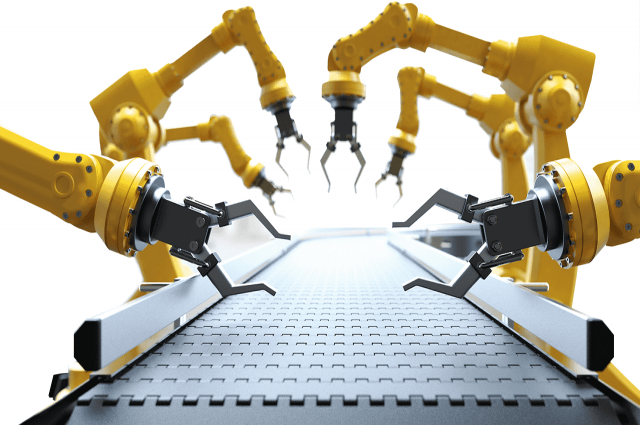
取得価額が10万円以上の固定資産は原則的には取得時の一時費用にはできません。
資産に計上して、毎期規則正しく「減価償却」していくことが会計上求められます。
税務上も減価償却費を損金算入できるのですが、会計の考えた方と微妙なずズレがあります。
今回のテーマは、固定資産の取得と減価償却の開始時期です。
Table of Contents
複数ある「取得」の考え方
固定資産を買ったとき、いつの時点で会計上資産計上すべきでしょうか?
普通は、その所有権を取得したときです。
では、所有権を取得したといえる時期とはいつでしょう?
その答えは税法にはないので、民法の考え方に従うことになります。
売買の場合、売主と買主の合意によって、いつでも目的物の所有権を移転させることができます(意思主義)。
これが取引による所有権移転時期の基本です。
売買契約書に「所有権の移転時期」について定めがあれば、当事者間ではそれに従うことになります。
もっとも、第三者がそれに対して異議をとなえることもあります。
例えば、同じ一つのモノが二重に売買されていて、買主が二人いる場合などは、どちらも売買によって目的物の所有権を取得したと主張できます。
そのようなときは、当事者の主観による意思主義でが埒が明かないので、客観的な基準でどちらが所有権を取得したかを決めることになります。
目的物が動産の場合は、その引渡しを先に受けた方が所有権を取得します(民法178条)。
不動産の場合は、不動産登記法等に従って先に登記を得た方です(民法177条)。
このように、当事者間だけでなく第三者に対しても所有権を取得したと堂々と主張できる状態を「対抗要件を備えた」とか「対抗要件を具備」といいます。
税法も基本的には、この考え方に従います。
契約にとくに問題がなければ「意思主義」です。
当事者の間で「先に目的物を引き渡す。代金は後払い」という約束があれば、たとえ代金の支払い期日が100年後でも、買主が所有権を取得するのは、引渡しの日です。
しかし、税務調査で意思主義による所有権移転が疑わしいとき(例えば、所有権移転時期を租税回避目的で恣意的にずらしていると疑われたとき、そもそも当事者間で売買があったか疑われるとき)には、調査官が対抗要件具備のときこそが所有権移転時期だと主張してくる可能性があります。
また、当事者の意思や引渡し時期がはっきりしないときには、実際にその目的物を占有して使用し始めた時期を所有権取得時期とみることもありえます。
物を取得したといっても、その時期が明らかでない場合は、いろいろ揉めそうです。
民法だけでなく税務上も物の取得時期は課税関係にかかわる重要事実です。
税務訴訟にまで発展した例も
固定資産の取得時期をめぐって納税者(法人)と国が争った事件があります。
今年に入って一審(東京地判平成30年3月6日)、高裁(東京高判平成30年9月5日)で判決がでていますが、いずれも納税者敗訴です。
争点は「いつから固定資産の減価償却を開始できるか」でした。
法人税法(以下「法」)は「各事業年度終了時において有する」減価償却資産につき一定の方法に応じて計算した金額の範囲内で減価償却費の損金算入を認めています(31条1項)。
つまり、事業年度末までに固定資産を取得できていなければ、その事業年度については減価償却費を損金算入することはできないということになります。
本件では、納税者(3月決算法人)の工場に平成25年2月に設置された機械装置を稼働させたものの、不具合が多く、検収が終了したのが5月に入ってからという状況でした。
納税者は事業年度末である3月末までに機械装置の引渡しを受けたと考えて、減価償却費を計上し、税務上も損金算入していました。
一方、国税当局は検収が終了するまでは引渡しを受けていないと考えて、減価償却費の損金算入を否認しました。
裁判所(東京高裁)は,控訴人が請負契約により「取得」した機械装置は,控訴人主張の事業年度で“設置”されているものの,“検収”等が行われたのは,その翌事業年度であるため,控訴人主張の事業年度で「取得」されたものとは認められず,減価償却費として損金算入できないと判断し、国の主張を認めました。
納税者側はこれを不服とし、最高裁に上告及び上告受理申立てしています。
契約内容に注意が必要
本件では機械装置という動産の「引渡し」時期が問題になっています。
問題の機械装置は、納税者からの発注をうけて製造されたものでした。
請負契約とは「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する」契約(民法632条)で、建物の建設、船舶の建造など、いわゆる「一点もの」の注文生産に利用される契約形態です。
東京高裁は、請負契約においては,注文者が請負人(製造者)から完成した請負の目的物の“引渡し”を受けることで目的物の所有権が移転するものと解し、本件のような,機械装置等を特定の場所に設置・稼働させることを目的とする請負契約で“引渡し”を受けたというには,単なる設置のみでなく,注文者による所要の性能を有することの確認等も必要であると判示しました。
その上で、本件機械装置が,平成25年3月期終了時点で「取得」されていない以上,25年3月期の減価償却費として損金算入できないと判断しました。
納税者は、本件機械装置は,「設置」から「検収」までの期間に一定の不具合が生じていたものの,稼働自体はしていたこと、減価償却資産の「取得」は,使用収益権限を実質的に含んでいればよいなど,企業会計における費用収益対応の原則との整合性についても主張していましたが、以下の理由を挙げて,納税者の主張を斥けています。
費用収益対応の原則は,企業会計において,期間損益を正確に把握するため,収益とそれを生み出すのに要した費用は同一会計年度に計上する原則。使用収益権限を取得すれば,減価償却資産の「取得」になるという結論は導き出されない。
本件では、
- 発注者と製造者が共に本件機械装置の全ての機能が問題なく動作するか確認すること
- 確認後に発注者が検収書に押印することで本件機械装置の検収が完了すること
- 検収と同時に成果物の引渡しがあったものとされること
等が請負契約の内容として具体的に定められていました。
これは請負契約としては一般的な内容と思われます。
こうした取り決めがある場合は、取り決めに従った検収が完了するまでは「引渡し」があったことにはできないということのようです。
しかし、特注品の製造設備などは、引渡しを受けたのち一定期間稼働させて初めて不具合に気づくこともあります。
本件では設置から検収まで3か月かかっています。
もちろん設備の仕様にもよるとは思いますが、試運転だけでは発見できない不具合まで確認しようとすると、そのくらいの期間は必要なのではないかという気もします。
そのあたりについては、上告審で最高裁がなんらかの判断をするかもしれません。
他の税金にも影響
東京高裁は、本件で示した解釈は、租税特別措置法の特別償却に係る規定や消費税法上の請負契約による資産の譲渡等(請負契約における所有権の移転及び引渡しの意義)についても同様に当てはまるとしています。
おそらくは、国税だけでなく地方税である償却資産税(固定資産税)についても同様に解されると思います。
***
開発を外部に委任したソフトウェア(無形固定資産)の減価償却についても、同じ問題が生じ得ます。
プログラムのバグは後々にならないと判明しないことが普通でしょうから、どこかで検収があったことにしないと、いつまでも「引渡し」が終わらないことになります。
そのあたりも、契約書の作りこみ方次第だと思いますが、それによって税務上の判断も拘束されることになりそうです。



