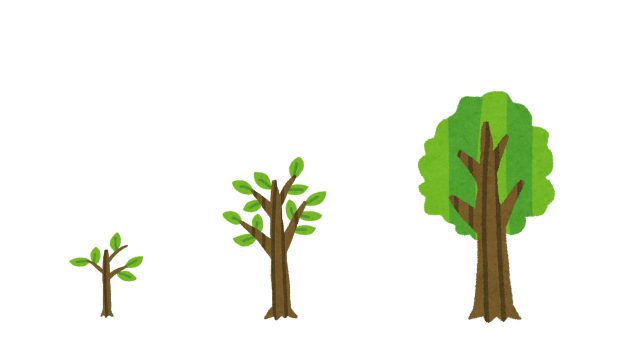前回からの続きです。
4.収益構造の変化
消費税・事業税に影響します。
(1)課税売上割合が著しく変動
消費税法上の概念として「課税売上割合」という割合があります。
簡単にいうと、全ての収入(売上だけでなく、受取利息などの営業外の収入、固定資産や有価証券の売却額など)に対して課税売上(消費税が課税される収入。免税売上も含む)が占める割合です。
消費税の確定申告書上で計算する割合で、これが高ければ仕入れに係る消費税をたくさん控除できます。
すなわち、この割合が高いほど納税額をセーブできます。
「調整対象固定資産」とよばれる一定の固定資産を買ってから3年以内の間に課税売上割合に「著しい変動」があった場合には、「調整対象固定資産」の仕入れに係る消費税の控除額を事後的に調整する必要があります(消費税法33条)。
「著しい変動」とは、3年間の平均の課税売上割合が「調整対象固定資産」の仕入れに係る消費税額について税額控除をした年の課税売上に比べて5%以上変動し、かつ、その変動割合が50%以上のことをいいます。
「調整対象固定資産」とは、「建物、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産でその価額が少額でないもの」(消費税法2条1項16号)をいいます。
「少額でない」とは一点あたり税抜きで100万円以上であることをいいます(消費税法施行令5条)。
つまり、長く使える100万円以上の資産ということです。
こうした高額な資産を購入するときに支払う消費税(仕入れに係る消費税)は高額になります。
固定資産の仕入れに係る消費税は、固定資産を取得した年の消費税の申告・納税額から控除できますが、その資産の使い方と申告方法によっては「課税売上割合」に応じた部分しか控除できません。
高額で長期間使用できる固定資産の仕入れに係る消費税額の控除額が、たまたまその資産を取得したある年の課税売上割合によって永久に固定されるのは不合理ともいえます。
こうした不合理さを是正するために、過去の仕入れにかかる消費税額の控除を事後的に調整する制度が設けられています。
一点100万円以上の設備投資をする場合は、それが「調整対象固定資産」にあたるどうか、その仕入れから3年以内に課税売上割合が「著しく」変動する可能性があるかどうかを検討しておくとよいでしょう。
ちなみに、この制度は有利にも不利にも働きます。
「著しく減少」すれば、過去に申告した控除額の一部を返上しなければなりませんから、将来の消費税納税額が増えます。
「著しく増加」すれば、過去に控除が足りなかった分を将来の消費税納税額から控除してもらえるので減税になります。
ただし、あまりにも長期間このような調整が続くのは納税者にも国にも負担になります。
そこで、仕入れのあった日から3年目の日が属する年・事業年度までに限って調整することになっています。
(2)業態変更
ア 消費税への影響
調整対象固定資産の使い方を変更すると税額控除の事後調整が必要になることがあります。
上記(1)と同じく、過去の仕入れ税額控除が不合理になることがあるためです。
過去3年以内に「個別対応方式」と呼ばれる申告方式で調整対象固定資産の仕入れに係る消費税額の控除を申告していた場合に問題となります。
「個別対応方式」とは、仕入れに係る消費税額をA「課税売上対応」B「非課税売上対応」C「その他」の3つに区分し、Aについては全額、Bについてはゼロ、Cについては「課税売上割合」に応じた額を控除税額とする申告方式です。
Aについては「課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整」(消費税法34条)が、Bについては「非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入れに係る消費税額の調整」(消費税法35条)が用意されています。
業態変更によって、それまで使っていた調整対象固定資産を課税業務用から非課税業務用に転用すると、過去の消費税申告で控除した税額控除を全額返上させられます。
逆に、非課税業務用から課税業務用に転用すると、将来の申告で全額控除できるようになります。
この転用にかかる事後調整も仕入れのあった日から3年目の日が属する年・事業年度まで限定されています。
イ 事業税への影響
一般の法人に対する事業税は各事業年度の所得金額を課税標準にしますが、電気供給業、ガス供給業、保険業及び貿易保険業を営む法人に対する事業税は各事業年度の収入金額とされています(地方税法72条の12)。
また、複数の都道府県に事業所等をもっている法人は、各都道府県に事業税を分割して申告・納税する必要があります。
このときの分割基準も業種によって異なります(地方税法72条の48第3項)。
例えば、一般的な法人の分割基準は各都道府県にある事業所等の数と従業員の数ですが、製造業の場合は従業者の数だけになります。
倉庫業、ガス供給業の場合は固定資産の価額が分割基準です。
収入金額課税の税率は所得金額課税の場合にくらべて低く抑えられていますが、経費を引く前の金額に課税されることになりますから、所得金額課税に比べて増税になることもあります。
分割基準の変更は、事業税総額をどう分割するかの問題なので、納税額にはそれほど影響しませんが、分割基準が変わることで申告作業の手間が増える可能性があります。
5.取引相手の拡大
消費税・源泉所得税に影響します。
(1)非居住者から電子データの購入
インターネットを介して国外の業者からデータやプログラムをダウンロードしたり、海外業者のクラウドサービスを利用すると消費税の課税関係が生じます。
以前は日本の消費税法がおよばない国外取引として「不課税」扱いだったものが、現在では課税対象になっています。
海外業者が日本で消費税の納税義務者になっている場合は、業者からの請求に応じて消費税を支払えばよいので、国内業者からの課税仕入れと同じです。
ただし、消費税の納税義務者として国税庁に届出をしていない業者から請求されて消費税を支払っても、その税額は消費税の申告上税額控除の対象にできません。
そのため、支払先の海外業者が日本の国税庁に「登録国外事業者」として届け出ているを国税庁が公表している事業者名簿で確認する必要があります。
海外業者が日本で消費税の納税義務者になっていない場合は、仕入れた側が海外業者に代わって消費税を申告・納税する制度が導入されています。
いわゆるリバースチャージ方式(消費税法5条)とよばれる方法です。
(2) 外国企業との業務提携
業務提携に関係して特許、商標、ノウハウなどの無体財産権の「使用料」を海外の提携先に支払うときには所得税の源泉徴収が必要になります(所得税法212条、161条1項11号)。
提携先の個人・法人の所在国によっては日本との「租税条約」を適用することで源泉税が軽減・免除されることがあります。
提携先との契約によっては、租税条約の適用とは無関係に税引き後の手取り額を決める内容になっていることもあります。
相手のペースにまかせて契約すると、源泉所得税や事務負担を一方的に押し付けらることになるかもしれませんから、源泉所得税を使用料の支払者と受領者のどちらが負担するのか、租税条約を適用するための手続きをどちらが主導するのかなど、契約の内容をよく検討する必要があります。
次回に続きます。
関連