租税条約と外国税額控除
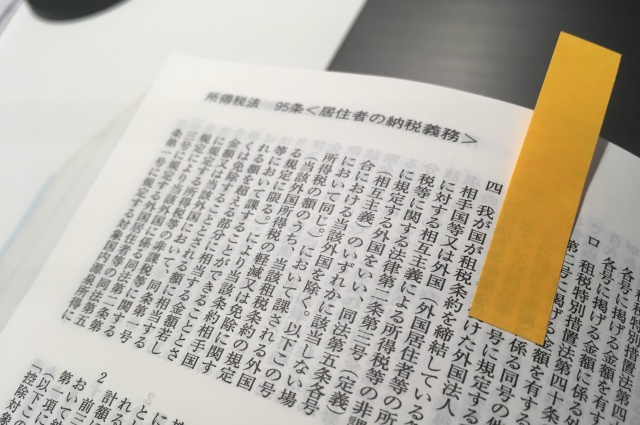
それを知らないと、誤った申告をしてしまうおそれがあります。
今回は、租税条約と外国税額控除の関係についてのお話しです。
Table of Contents
租税条約とは
「二重課税回避」と「脱税防止」を主な目的とする条約・協定のことです。情報交換協定、税務行政執行共助条約を含めて「租税条約」と呼ぶこともありますが、ここでは前者の意味(狭義)の租税条約を取り上げます。
2019年5月現在日本は71か国・地域と61の「狭義」の条約を締結しています(旧ソ連・旧チェコスロバキアとの条約が複数国へ承継されていることから、条約等の数と国・地域数が一致しません)。
租税条約と国内法の関係の詳細については、ブログ「租税条約と日本の税法」をご参照いただければと思います。
外国税額控除とは
国際的二重課税を排除する税制です。
国外源泉所得に対して課税された外国の所得税・法人税(外国税額)を日本の所得税・法人税の額から控除し、残額を国に納税させる仕組みになっています。所得税・法人税の額から外国税額を控除しきれないときは、一定条件のもと地方税からの控除もできます。
その仕組み・考え方の詳細については、ブログ「外国税額控除について」をご参照ください。
外国税額控除は、あくまでも「国外源泉所得」に対して課された外国の「所得税・法人税」が対象なので、国内源泉所得に課された税金や、所得税・法人税以外の税金は対象外となります。
租税条約の適用対象者
締約国の居住者でなければ、租税条約は適用されません。
基本的には各締約国の国内法によってその国の居住者となる個人・法人が、租税条約上も締約国の居住者ということになりますが、まれに双方の国内法でそれぞれの国の居住者になってしまうことがあります。
租税条約では、そのような場合にいずれか一方の締約国の居住者として認定する取り決めも定めています。
租税条約の特典
税負担を減免し、締約国間での投資・貿易を促進しようという趣旨から、各締約国が課税できる税率の限度(軽減税率)を定めていることが通例です。
例:日米租税条約の場合
原則:日本の居住者がアメリカ法人から支払いを受ける配当に対しては30%の所得税(連邦税)が課税(源泉徴収)される。
条約:議決権のある株式の所有割合に応じて所得税率が10%、5%または0%に軽減される(条約10条)。
届出無くして特典なし
条約が国内法に優先適用されるのが国際法の基本ルールですが、実際には条約の適用要件を満たしてることを税務当局に届出しなければ、条約の特典を受けられません。
事前届出がなければ国内法どおりに課税されてしまいます。
事後届出で還付請求することも可能ですが、国によっては手続きに時間がかかることもあります。
例:日米租税条約の場合
日本の法人がアメリカの法人から支払いを受ける配当所得について租税条約の特典(軽減税率)を受けたいときは、以下のような届出書(W-8BEN-E)を源泉徴収義務者(配当を支払うアメリカ法人やその取扱いをする金融機関)を通じて内国歳入庁に提出します。
日本法人のプロフィール(Part I)のほか軽減税率の適用区分やその根拠となる条約の条項など(Part III)で届出します。
ちなみに、W-8BEN-EのPart IはFATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)の告知書も兼ねている(No.5)ため、条約の特典を受ける必要がない場合にも、源泉徴収義務者から提出を求められることがあります。
特典制限条項(LoB Clause)に注意
租税条約上の締約国の居住者に該当する者であっても、租税条約の定めによって、条約上の特典の享受を制限されることがあります。
以下の国との租税条約にはそのような特典制限(LoB: Limitation on Benefit)の定めがありますので、注意が必要です。
アメリカ、イギリス、フランス、オーストラリア、オランダ、スイス、ニュージーランド、スウェーデン、ドイツ、ラトビア、リトアニア、エストニア、ロシア、オーストリア、アイスランド、デンマーク
LoBがあると、締約国内に企業活動の実態があるといえるかをテストを経なければ条約の特典を受けられない仕組みになっています。
例えば、日米租税条約の場合、日本法人でもその発行する株式の50%超が第三国の居住者に所有されている場合や、課税所得の計算上必要経費・損金の額に算入できる金額の50%超が第三国の居住者に支払われている場合などは、日本に企業活動の実態がないとみなされて条約の特典が制限されてしまいます(条約22条)。W-8BEN-Eでは、どのような要件を満たしてテストをパスしたかをNo.14(Part III)で自主申告することになっています。
かっての租税条約の濫用(トリーティ・ショッピング)に対する抑止策として導入されたものです。「ダッチ・サンドイッチ」の当事国であるオランダも現在はLoB準拠型の条約締約国の一つです。
外国税額控除には制限がある
ここから国内法に戻ります。
高率負担部分は対象外
法人税の外国税額控除にあたっては実効税率35%を超える部分の控除ができません(法人税法69条1項・法人税法施行令142条の2第1項)。
また、金融・保険業を営む法人や所得金額のうち利子所得の占める割合が比較的大きい法人が受け取る利子所得に対する外国税については、その法人の所得率に応じて、10%または15%を超える部分の控除が制限される場合があります(法人税法施行令142条の2第2項)。
租税条約の限度税率を超えて課税された部分は対象外
高率負担部分にあたらなくても、租税条約の締約国で課税された外国税については、条約が定める限度税率を超えて課税された部分の控除はできません。(所得税法95条1項・所得税法施行令222条の2第4項4号、法人税法69条1項・法人税法施行令142条の2第8項5号)
日本での課税額を超えて課税された部分も対象外
国内法に加えて、租税条約の規定によっても外国税額控除が制限されます。
これまで日本が締結した租税条約には「二重課税の排除」という条項があり、そこでは「ただし、控除の額は、当該所得に対する日本国の租税の額を超えないものとする。」という一文が加えられています(例:日米租税条約23条)。
したがって、たとえば、日本で5%で課税される所得に対して外国で10%の所得税が課されていた場合は、日本で控除できる外国税は5%までということになります。
一方の締約国における課税額を超えて他の締約国で課税された部分は「二重」ではなく「追加」課税であり、外国税額控除の目的である二重課税の排除・軽減の埒外だと考えているようです。
控除額は限度額の範囲内で
上記のような制約によって絞り込まれた控除対象外国税であっても、実際に所得税・法人税から控除できる金額は、「控除限度額」の範囲内に限られます。控除限度額は、簡単にいうと、課税所得金額のうちに国外源泉所得が占める割合を所得税・法人税の額(外国税額控除前の額)に乗じた金額です。
控除限度額の計算の要となる国外源泉所得の額は、国内法の規定に基づいて計算するのが原則ですが、租税条約が適用される場合には注意が必要です。なぜなら、その所得の源泉地国(所得が発生した場所のある国)が条約の規定によって修正され、場合によっては国内法で国外源泉所得とされるものが、国内源泉所得になったり、その逆の取扱いをうけることがありうるからです。その場合には、控除限度額計算上の国外源泉所得の額も租税条約の規定に従って計算する必要があります。
なお、その年・事業年度の控除限度額が十分になく、控除しきれない金額が生じてしまった場合は、翌年以降3年間の繰越し控除が認められます(所得税法95条2項、法人税法69条2項)。逆に、控除限度額が余った場合は、限度額を3年間繰越して利用することができます(所得税法95条3項、法人税法69条3項)。
***
外国税額控除のための限度額計算は実際は複雑な構造になっており、租税条約も参照しなければならない場合もあるので、なかなか実務上の難易度が高い分野です。まずは、所得の源泉地国と日本の間に租税条約が締結されているかどうかをチェックしてみてください。



